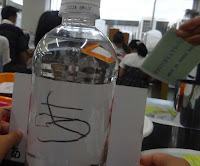6月20日(木)に大人が学ぶサイエンス講座が開講されました。今回のテーマは「家庭で楽しむ科学(サイエンス)クッキング」です☆水で洗う、火で温める、混ぜるなど…「料理」と「科学の実験」ってよく似ています(^^)/今回は、「琥珀糖」と「三食蒸しパン」2つのスイーツをつくりました◎
~食べられる宝石「琥珀糖」づくり~
琥珀糖のもとは寒天液です。寒天は鎖のような長い分子をもった多糖類。その絡み合った鎖のなかに水分をたっぷり閉じ込めることができます。寒天と一緒に溶かされた砂糖などの物質は、温度が下がると表面に結晶化として出てきますが、水分は寒天の中に閉じ込められます。そのため、外見はちゃんと固まっていますが、中はプルプル!シャリシャリ!とした食感をもった琥珀糖をつくることができます★
寒天液は、粉寒天、水、砂糖を沸騰するまでお鍋で温めます。食紅をいれなくても、透明で綺麗な琥珀糖ができますが、今回は寒天液に食紅で色をつけました。色をつけると、より涼しげでおしゃれな琥珀糖を作ることができます☆彡~カラフル三食蒸しパンづくり~
こちらは酸性、中性、アルカリ性の特徴を生かして、蒸しパンに色をつけるお菓子作りです。この3つのタイプはよく理科の授業で耳にしますよね。野菜の中、とくに紫キャベツ、ナス、紫イモなどは、この液性を調べることができるアントシアニンという成分がたくさん入っています。 まさに科学的な視覚で楽しめるクッキング!!どんな色かは、ぜひ作って確かめてみてくださいね(^_-)-☆(…写真に答えが!) 見た目があっ、、、という色もありましたが、お味はなかなかのおいしさ!!!(^^)!ご家庭で、とくに親子でつくると盛り上がりそうですね!
まさに科学的な視覚で楽しめるクッキング!!どんな色かは、ぜひ作って確かめてみてくださいね(^_-)-☆(…写真に答えが!) 見た目があっ、、、という色もありましたが、お味はなかなかのおいしさ!!!(^^)!ご家庭で、とくに親子でつくると盛り上がりそうですね!