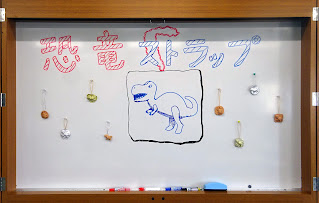12月19日「雪が舞うクリスマスボトル」が開講されました。科学の力で、クリスマスにぴったりなスノードーム「クリスマスボトル」と「鏡のクリスマスカード」をつくりました。
今回は「おとなが学ぶサイエンス講座」ということで、作品作りだけでなく、まずは今回の講座内容に関する科学のお話。一般的なスノードームは、透明でドロッとした液体の中を、プラスチックやアクリル樹脂の白く小さな粒がふわふわ漂うことで、雪が舞っているように見えるオブジェです。
そして、今回作るクリスマスボトルは、サンタやトナカイなどクリスマスらしい人形が立っている無色透明の液体ボトルが、室内の窓際など気温の低いところに置いておくと、白い雪のような結晶がひらひらと舞い落ち、まるで雪が積もったように人形の周りを彩る、科学の力を使ったXmasオブジェです。
これは、温度による薬品が水へ溶ける量(溶解度)の違いを利用しています。砂糖や食塩などは、それぞれ水に溶ける限界の量が決まっていて、それ以上溶かそうとすると、溶け残りが出てしまいます。水に溶けるものの中で、温度によって溶ける量が大きく変わるものの一つが、今回用いた「塩化アンモニウム」。塩化アンモニウムは、冷たい水には少ししか溶けませんが、水の温度が上がれば上がるほどたくさん溶けます。
まずは、そのことを実験で確かめました。試験管の中に入った塩化アンモニウムに、駒込ピペットを使って水を入れます。こんままだと、いくら混ぜても白くにごって溶け切りませんが、湯煎にかけて水の温度を上げると…完全に溶けて、無色透明な溶液になりました。
そして、お楽しみはここから! お湯で温めることで溶ける量を増やしているので、お湯から出したまま置いておき、自然に水の温度が下がると… 溶けていたはずの塩化アンモニウムの結晶が水面から落ちてきます(再結晶)。無事みなさんが、再結晶を確認したところで、いよいよ「雪が舞うXmasボトル」を作ります。
塩化アンモニウム90gと、メスシリンダーでぴったり200ml量った水を混ぜながら、アルコールランプの火にかけます。ガチガチに固まって一見溶けなさそうな塩化アンモニウムの塊も、水の温度が上がると魔法のように溶けて見えなくなります。
 塩化アンモニウムが完全に溶けて、液が無色透明になったら、アルコールランプの火を消し、温かいうちに飾りの人形を入れたボトルに注ぎます。この時、気泡が入らないように慎重に内蓋を閉めてから、外蓋をしっかり閉めたら完成です。
塩化アンモニウムが完全に溶けて、液が無色透明になったら、アルコールランプの火を消し、温かいうちに飾りの人形を入れたボトルに注ぎます。この時、気泡が入らないように慎重に内蓋を閉めてから、外蓋をしっかり閉めたら完成です。
ボトルの中を舞う雪を楽しんだ後は、もう一つのクリスマスグッズ。鏡シートを使った「鏡のXmasカード」を作ります。こちらは鏡の反射を利用しています。左右2枚の鏡をそれぞれ別々に飾り付け、カードを折り重ねると、合わせ鏡となり、それぞれの模様が重なって素敵なデザインを楽しむことができるカードです。折る角度を変えることで、いろんな表情を楽しむことができます。
飾りつけの途中で左右で映し、何度も見え方を確認しながら、皆さん長時間集中して、自分だけのオリジナルカードを作りました。
今回の実験では、駒込ピペット、アルコールランプ、メスシリンダーなど、小中学校以来の実験器具を思い出しながら使ったり、難しい工程では初対面の方同士でもお互い仲良く助け合ったりしながら、楽しく活動されていました。Xmasボトルに用いた塩化アンモニウムは、肥料や食品添加物としてホームセンターなどで手に入るものもあります。気になった方は、ぜひ作ってみてくださいね。
今回のような、おとなが学ぶサイエンス講座は、年に4回開催しています。今回のような科学工作の他に、科学の力を確認しながら行うクッキングや、 アクセサリー作り、お茶を科学する講座など、年によって内容も様々なので、気になった方はぜひ、科学センターホームページで確認してみてくださいね(゚∀三゚三∀゚) ウホー!。